ジャズサンビスタス
レビュー
Sambrasa Trio / Em Som Maior
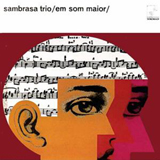
tracks:
- Sambrasa (3:43)
- Aleluia (3:13)
- Samba Novo (2:43)
- Clerenice (2:16)
- Duas Contas (2:40)
- Nem O Mar Sabia (2:27)
- Arrastão (4:20)
- Coalhada (3:09)
- João Sem Braço (3:43)
- Lamento Nortista (3:20)
- A Jardineira (1:55)
member credit:
- Hermeto Pascoal (piano & flute)
- Humberto Clayber (bass & harmonica)
- Airto Moreira (drums)
release year:
1965
label:
Som/Maior
review:
キラーチューン「Samblues」で知られるSambalanço Trio(サンバランソ・トリオ)は、2作目をリリースするとSom Três(ソン・トレス)とSambrasa Trio(サンブラーザ・トリオ)という2つのピアノトリオに分かれてしまいます。前者はピアニストCésar Camargo Mariano(セザール・カマルゴ・マリアーノ)がJongo Trio(ジョンゴ・トリオ)のベースSabá(サバー)、ドラムAntonio Pinheiro(アントニオ・ピネイロ:トニーニョ)と結成。本稿の主役となる後者は、ベーシストHumberto Clayber(ウンベルト・クライベール)とドラマーAirto Moreira(アイルト・モレイラ)が、Conjunto Som 4(コンジュンオ・ソン・クァトロ)というトランペット入りのカルテットのメンバーだったHermeto Pascoal(エルメート・パスコアル)と組んで結成されたピアノトリオです。この分裂劇が解散だったのか、はたまた誰かが脱退したことによるものだったのか、真相ははっきりしませんが※1今となってはいろいろなジャズサンバの作品が楽しめなんとも嬉しい限りです。とは言っても、Sambalanço Trioはこの後、それまでの2作が好評を博したことをうけ再会セッションを行い3作目を作ることになりますが。
本作はそんなSambrasa Trioが1965年に発表したアルバム。原盤元は、この年Audio Fiderity(オーディオ・フィディリテイ)から社名変更したSom/Maior(ソン・マイオール)。そのSom/Maiorからリリースする作品ということで『Em Som Maior』というタイトルになったと思われます。2006年にSOM LIVRE MASTERSシリーズとしてゴソっとリイシューされた作品の中の一枚。同シリーズは先述したSom TrêsのファーストやSambalanço Trioの3作目をはじめとし、Bossa Jazz Trio(ボッサ・ジャズ・トリオ)のファースト、Sambossa 5(サンボッサ・シンコ)のファースト、Manfredo Fest(マンフレッド・フェスト)の初リーダー作『Bossa Nova...Nova Bossa』、Sansa Trio(サンサ・トリオ)のファースト、オルガニストWarter Wanderley(ワルター・ワンダレー:ヴァルテル・ヴァンデルレー)の覆面バンドQuarteto Bossamba(クァルテート・ボッサンバ)など、ジャズサンバ関連作だけでも充実のカタログを誇りますが、本作はその中でも群を抜いて重要な作品であることは間違いないでしょう。
アルバムジャケットも秀逸。部分的に使われているこの譜面は「Quem É Homem Não Chora」という曲。Vera Brasil(ヴェラ・ブラジウ)とGeraldo Vendré(ジェラウド・ヴェンドレー)による楽曲で、「男は泣くな」とか「誰も泣かない」といった邦題がついています。本作にこの曲が収録されているわけではないのですが、前身バンドであるSambalanço Trioが米国人歌手Lennie Dale(レニー・デイル)のバッキングを務めたELENCO盤に収録されているのでまったく関係がないというわけでもない。この曲で一番有名なのはやはりManfredo Fest Trioの高速ジャズサンバでしょう。それにしてもこの『Em Som Maior』を筆頭にSom/Maiorのジャズサンバ作品ってビジュアル的なコンセプトに統一感がありますよね。ボサノヴァというとELENCOのモノトーン+赤というデザインが思い浮かぶように、ジャズサンバというとここらへんのアートワークを連想します。
アルバムはAirto Moreiraのオリジナル、'Sambrasa'でガツンと幕をあけます。ドラムをフューチャーした性急なイントロパートから、ゆったりとしたテンポの2コードによるヴァンプへ。Hermeto Pascoalのソロラインは少しの淀みもなく高速フレーズを連発。ベースソロでは典型的なHumberto Clayber節を存分に堪能できます。Airto Moreiraのドラムソロ後はテンポアップして高速ジャズサンバ。フェイドアウトするので結局曲のテーマメロディはあまり印象に残らなかったりしますが、のっけからハードな演奏に圧倒されます。
続く'Aleluia'はElis Regina(エリス・レジーナ)のヴォーカルバージョンでも有名なシンガーソングライターEdu Lobo(エドゥ・ロボ)による楽曲。Aメロをルバート気味に演奏し、Bメロからオーソドックスなジャズサンバスタイルに移行します。ガッツリ3人のソロスペースが取られていて、演奏自体はジャズのフォーマットに則っています。
'Samba Novo'は、ジャズマニアDurval Ferreira(ドゥルバル・フェレイラ)によるハードコアなジャズサンバスタンダード。ボサノヴァでもMPBでもない、こういうジャズ好きが作ったオリジナルを立て続けに選曲してこられると骨のあるバンドだなと感じてしまいます。テーマ後のやたら切羽詰まったアウトロも印象的。
4曲目の'Clerenice'はJosé Neto Costa(ジョゼ・ネト・コスタ)という人物が作曲した爽やかなミディアムジャズボッサ。Bメロでワルツ風に拍を分割するところが面白く感じます。ピアノソロの途中で「Desafinado」を引用するあたりのHermeto Pascoalのセンス、カッコ良いですね。ここまでの曲間の繋がり・流れは素晴らしいの一言に尽きます。
'Duas Contas'はアルバム唯一のバラードによる演奏。どこかねっとりとしたピアノのソロラインと、バラードでも基本攻めるバッキングのベース、ドラムが聴いていて飽きを感じさせません。
ハーモニカイントロで始まる'Nem O Mar Sabia'はRoberto Menescal(ホベルト・メネスカル)とRonaldo Bôscori(ホナルド・ボースコリ)による作曲。ハーモニカというとHumberto Clayberということになるのですが、このイントロではベースも鳴っているのでそうすると、多重録音で後からハーモニカの音を被せたのでしょうか。ただアルバムでは一貫してHermeto Pascoalが左チャンネル、Humberto Clayberが右チャンネルであることと、ピアノのフレーズがコードを押さえただけのシンプルな演奏に終始していることから、実はHermeto Pascoalがピアノを弾きながらハーモニカを吹いてるじゃないかとか、ひとり妄想しています。テーマからはハチロク的なリズムで、ピアノ、ベース、ドラムとソロを回していきます。このバンドのソロ回しは無伴奏で放り投げるという形が多いですね。ブツッと途切れる印象は否めませんが、一発勝負の緊張感はバシバシ伝わってきます。
Edu LoboとVinicius De Moraes(ヴィニシウス・ヂ・モラエス)の共作である'Arrastão'は、やはりElis Reginaの熱唱で有名な曲。マーチングドラムの上でフルートとハーモニカがユニゾンイントロ。Aメロは3+3/3+2という符割の変態拍子、サビから2/4拍子のジャズサンバスタイルでアレンジされています。かなり長めのベースソロの後、堰を切ったようなドラムソロ。サビ部分を再現し、ドラムソロ後にお決まりともいえるヴァンプによる高速ジャズサンバ。その後に戻りのテーマが続き、サビを元にしたアウトロまでしっかりアレンジされています。
'Coalhada'はHermeto Pascoalが作曲したオリジナル。この曲は後に「ブラジルの奇才」と称されるHermeto Pascoalの才能を遺憾なく発揮しています。曲の途中でワルツ風に拍を分割しつつさらにそれを2つに割ったり、5/8拍子になったり極めて忙しい。ソロではさすがに普通の拍子に戻りますが、それでも小節数が4の倍数ではないのでソロしにくいかもしれません。ちなみにHermetoはピアノソロの途中で「A Morte De Um Deus De Sal」を引用しています。各人のソロ後、テーマに戻りまたしてもヴァンプ、その後はテンポダウンするアレンジ。ちなみに曲名は「凝乳(ぎょうにゅう)」という意味。作曲者Pascoalの最後の4文字に引っ掛けているのでしょうか。
いわゆるステレオタイプ的な東洋風のメロディから始まる'João Sem Braço'はベーシスト、Humberto Clayberのオリジナル。威勢の良いヴァンプをベースにしたインプロ勝負の楽曲。ピアノソロに続き火を吹くようなドラムソロが終わった後はピアノそっちのけでフルートソロ。さらに破天荒なベースソロが続く。3人の即興能力の高さには舌を巻くばかりです。
続く'Lamento Nortista'もHumberto Clayberによる作曲。フルートとハーモニカのユニゾンイントロ。前半こそ落ち着いたミディアムテンポながらも、ハーモニカの演奏が開始されると一気にボルテージが上がり、厳しい表現に変わっていきます。まさにジャズサンバの面目躍如といった熱さ。最後はハーモニカによるテーマ演奏で締められます。数あるジャズサンバの演奏の中でも一、二を争う熱気ではないでしょうか。
ラストは'A Jardineira'。Benedito Lacerda(ベネジット・ラセルダ)とHumberto Porto(ウンベルト・ポルト)という二人による作曲です。もともとはショーロの楽曲なのでしょうか。※2テーマの途中で一瞬テンポルバートになりますが、基本的には終始ミディアムアップの明るい曲調です。テーマが演奏されるとドラムソロがフューチャーされます。その後お約束的に2コードによるヴァンプに突入しますが、Hermetoのきらびやかな高音フレーズとAirtoのカップショットが、なんとも気持ちよい聴き終わりの印象を与えてくれます。なんだか運動後の爽快感に似てますね。
正直に申し上げますと、ピアノ、ベース、ドラムという3つの楽器による伴奏を伴わないハーモニカ/フルートの演奏ってどこかスカスカに感じていた節があり、本音を言えば純粋なピアノ、ベース、ドラムだけの表現が聴きたかったなと思っていたのですけれども、結果としてSambrasa Trioというとハーモニカとフルートというのが条件反射的に思い浮かんでくるので、バンドのカラーとして重要なファクターになっているのかもしれません。今回レビューにするにあたり何度も聞き返してみてそういう風に思えるようになりました。
それにしてもこのアルバム、音がはっきりしていて迫力がありますね。この音の良さというのが演奏内容と相まって本作の評価をさらに押し上げているような気がします。ハードコアな選曲と、高度な演奏技術、そして最高に熱いインプロ。インプロ重視型ジャズサンバの最右翼です。
- ※1 ブラジル民族文化研究センター研究員・青木義道氏の「2. アイルト・モレイラ:音の伝道師」という文章には「1964年、ピアノのセーザル・カマルゴ・マリアーノが抜け、新たにピアニストとして鬼才エルメート・パスコアルを迎えて、トリオはサンブラーザトリオと名前を変える」とあります。一方、『ボサノヴァ・レコード辞典』(宮坂不二生氏監修)の板橋純氏が担当されたSambrasa Trioの項には、「才人として尊敬されるエルメート・パスコアル(p)に、サンバランソ・トリオを抜けたクレイバー・ジ・ソウザ(b)、アイルト・モレイラ(ds)の3人で、多分64〜65年に組まれていたジャズ・サンバのトリオ」とあります。
- ※2 「Benedito Lacerda」で検索するとショーロ専門サイト「fonfon for choro music」というサイトにヒットします。作者に関しては「作曲家列伝 Benedito Lacerda(ベネジット・ラセルダ)」のページをご参照ください。
(2012.09.02)